住所 :茨城県鹿嶋市宮中2306−1
電話 :0299821209
社務所 :平日 8:30~16:30
公式HP:http://kashimajingu.jp/
Wiki : 鹿島神宮
■ はじめに
茨城県鹿嶋市に鎮座する「鹿島神宮(かしまじんぐう)」は、常陸国一之宮にして、全国に約600社ある鹿島神社の総本社です。創建は神武天皇即位以前とも伝わるほど古く、日本神話の時代から国を護る「武の神」として篤く信仰されてきました。
その長大な歴史と神聖な森の中に漂う気配は、訪れる人々に深い感動と畏敬の念を抱かせます。
■ 御祭神
武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)
日本神話に登場する雷神であり、剣の神・武道の神・勝運の神として知られます。天照大神の命を受け、出雲の国譲りにおいて大国主命に国を譲らせたことで有名です。
その剛勇と神威は、日本書紀にも記されるほど。鹿島神宮はまさに「武神の総本山」といえる神社です。
詳細は別ページでまとめていますので、こちらの記事もご覧ください。
■ 由緒・歴史
鹿島神宮の創建は神武天皇即位の年よりも古いと伝わり、『常陸国風土記』や『日本書紀』にもその名が見られます。
古代から国家鎮護の中心的役割を担い、奈良時代には藤原氏の氏神としても厚く崇敬されました。
平安時代には延喜式名神大社に列し、伊勢神宮に次ぐ格式の高さを誇りました。
中世以降も源頼朝、徳川家康など多くの武将が参拝し、戦勝祈願を捧げています。
特に家康は江戸幕府の平安を祈念し、社殿の修築を命じました。
■ 主な見どころ
◉ 一之鳥居(東日本最大の鳥居)
鹿島港近くに立つ巨大な鳥居。高さ約18メートルもあり、青銅製としては日本最大級です。海上からも見えるその姿はまさに鹿島の守護神の象徴。
◉ 樹齢千年の「御神木」
境内の奥には、樹齢千年以上の杉がそびえ立ちます。神域を守るようにそびえるこの巨木からは、長い年月を経た神聖な力を感じることができます。
◉ 要石(かなめいし)
鹿島神宮の象徴的なパワースポットのひとつ。
地震を起こすとされる大鯰(おおなまず)の頭をこの石で押さえていると伝えられ、昔から「地震封じの石」として信仰されています。
ちなみに、香取神宮にも同様の要石があり、両社で日本を支えているといわれます。
要石については別のページで詳しく解説しているのでそちらをご覧ください
◉ 奥宮(おくのみや)
現在の奥宮は、慶長10年(1605年)に徳川家康が関ヶ原の戦勝を感謝して奉納した本殿を移築したもの。
堂々とした朱塗りの社殿は国指定重要文化財にも指定されています。静寂な森の中に佇むその姿は、まさに神域の中心。
◉ みたらしの池
参道の奥にある清らかな泉。
昔はこの池で身を清めてから神前に参拝したといわれています。
澄み渡る水面には木々が映り込み、まるで異界と現世の境界のような神秘的な空間です。
■ 鹿島神宮と香取神宮・息栖神社の関係
鹿島神宮は、香取神宮(千葉県)・息栖神社(茨城県)とともに「東国三社」と呼ばれています。
三社を巡拝すると伊勢参りに匹敵する功徳があるといわれ、古くから多くの参拝者が「東国三社まいり」を行ってきました。
特に江戸時代には庶民の憧れの信仰旅行地として賑わいました。
■ 交通アクセス
- 所在地:茨城県鹿嶋市宮中2306-1
- アクセス:JR鹿島線「鹿島神宮駅」から徒歩約10分
- 駐車場:あり(無料・有料あり)
■ まとめ
鹿島神宮は、単なる「武の神社」ではなく、日本の歴史と信仰の原点に立つ場所です。
その広大な神域には、太古の神々が今も息づいており、参道を歩くだけで心身が清められるような感覚を覚えます。
ぜひ、香取神宮・息栖神社と合わせて「東国三社巡り」を行い、日本の神々が守る東の地の神威を肌で感じてみてください。

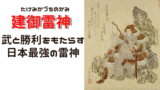


コメント