
■ 多賀大社系とは
滋賀県犬上郡多賀町に鎮座する「多賀大社(たがたいしゃ)」は、古来より「お多賀さん」と呼ばれ親しまれてきた神社です。延命長寿・縁結び・厄除けの神として篤い信仰を集め、その分霊を祀る「多賀神社」は全国に約240社以上あるといわれます。この多賀大社を中心とする信仰圏を「多賀大社系」と呼び、日本神話の根幹を担う神々を祀ることから、天皇家をはじめ広く民間にも深く浸透してきました。
■ 主祭神
伊邪那岐大神(いざなぎのおおかみ)
伊邪那美大神(いざなみのおおかみ)
この二柱の神は、日本神話における国生み・神生みの夫婦神です。『古事記』『日本書紀』では、日本の国土と多くの神々を生み出した創造の神として登場し、生命の源・縁結び・子授け・延命の神として古くから信仰されてきました。
特に多賀大社では、伊邪那岐大神が黄泉の国から戻り、禊によって清められた後に御神徳を顕したことから、「再生」「蘇り」の象徴としても崇められています。
■ 全国の主な多賀神社
多賀大社の分霊は、近畿地方を中心に全国へ広がり、特に「延命・長寿」「良縁」「家内安全」を願う人々によって勧請されました。以下はその代表的な神社です。
- 多賀大社(滋賀県犬上郡多賀町)
総本社。創建は神代にまで遡るとされ、天智天皇が病を癒した際に勅願を奉げた伝承を持つ。江戸時代には「お伊勢参り」「お多賀参り」と並ぶほどの人気を誇り、多くの庶民が参拝に訪れた。 - 多賀神社(兵庫県神戸市兵庫区)
平安時代に多賀大社から分霊を勧請。港町神戸の守護神として信仰され、厄除け・開運の神として地元で親しまれている。 - 多賀神社(東京都新宿区)
江戸時代に滋賀の多賀大社を勧請したとされる。都心にありながら静寂な雰囲気を保ち、寿命長久・良縁祈願の参拝者が多い。 - 多賀神社(福岡県北九州市)
九州における多賀信仰の中心的存在。伊邪那岐・伊邪那美両神を祀り、家族円満や再生の御利益を求める人々に崇敬されている。 - 多賀神社(北海道札幌市)
開拓時代に滋賀県出身者が勧請した神社。寒冷地における「無病息災」「生命の守護神」として信仰を集めている。
■ 多賀大社系の特徴
- 延命長寿・蘇りの神としての信仰
多賀信仰の根底には、「命をつなぐ」「再び立ち上がる力」を授ける神徳があります。戦国武将から庶民まで、病気平癒や長寿祈願の神として篤い信仰を集めました。 - 夫婦和合・縁結びの象徴
伊邪那岐・伊邪那美の二柱は日本神話最初の夫婦神であり、家庭円満や良縁祈願の信仰が全国に広がりました。結婚式や夫婦守護のお守りが有名です。 - 「お伊勢参り」と並ぶ「お多賀参り」
江戸時代には「お伊勢参り」「お多賀参り」「金比羅参り」が庶民三大参詣として知られました。伊勢神宮が「天照大神」、多賀大社がその親神とされ、「伊勢へ七度 多賀へ三度」といわれるほどの人気でした。 - 多賀杓子(たがじゃくし)
多賀大社の授与品として有名な「多賀杓子」は、「命をすくう」「寿命を延ばす」という縁起物。各地の多賀神社でもこの杓子が授与されることがあります。
■ 神仏習合の影響
中世から近世にかけて、多賀信仰は仏教と深く結びつきました。伊邪那岐大神・伊邪那美大神は、次の仏と習合しました。
- 大日如来(だいにちにょらい):天地開闢・創造の神としての側面が、宇宙の根本仏である大日如来と習合。
- 阿弥陀如来(あみだにょらい):再生・救済・長寿の象徴として信仰された。
- 観世音菩薩(かんぜおんぼさつ):慈悲と癒しの力が伊邪那美神の神徳と重ねられた。
多賀大社自体も中世には多賀山金剛輪寺(天台宗)などの僧侶によって管理され、神仏習合の姿が見られました。仏教では「延命地蔵尊」「寿命延長観音」などとも関係づけられ、命の守護神としての信仰がさらに強まりました。
■ まとめ
多賀大社系の神社は、「生命」「縁」「再生」を司る神々を祀る神社として、古くから日本人の心のよりどころとなってきました。
それは、病気や災厄に打ち勝ち、家族や縁を大切にして生きるという、日本人の根本的な祈りを体現しているともいえます。
多賀の神々は、今日も「いのち」を尊ぶ信仰として生き続けています。
全国の「お多賀さん」を訪ね歩けば、時代を超えて受け継がれてきた「再生と希望の祈り」に触れることができるでしょう。
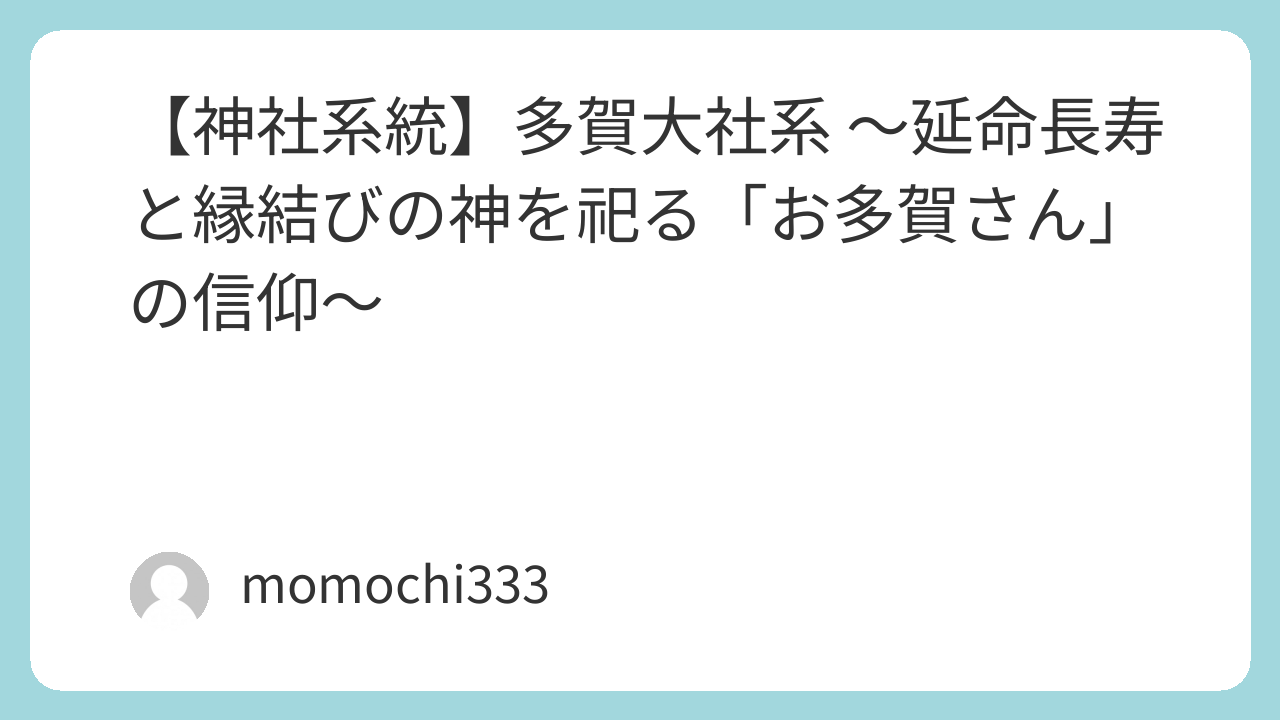

コメント