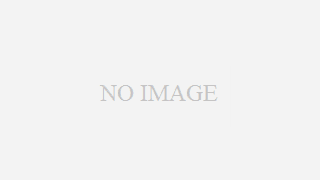 時短・効率化
時短・効率化 【神社めぐり】天神社になぜ牛がいるの? 〜菅原道真と神使・牛の深い関係〜
全国の「天神社」や「天満宮」を訪れると、境内のどこかに牛の像が鎮座している光景をよく目にします。撫で牛(なでうし)と呼ばれるその像は、頭や体を撫でると「学問が上達する」「病気が治る」などのご利益があるとされ、多くの参拝者に親しまれています...
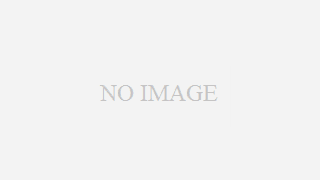 時短・効率化
時短・効率化 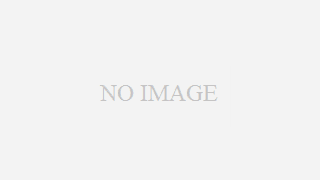 神様図鑑
神様図鑑 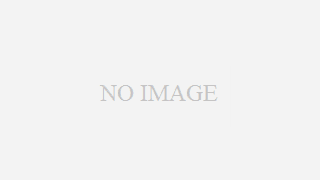 神様図鑑
神様図鑑 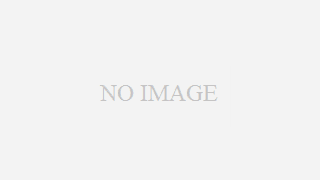 【神社めぐり】
【神社めぐり】 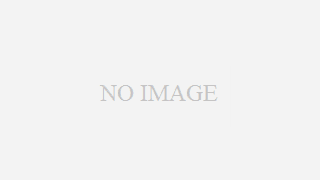 【お寺めぐり】
【お寺めぐり】 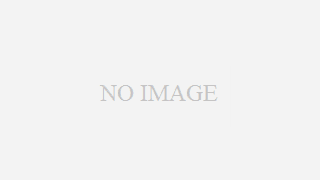 【神社めぐり】
【神社めぐり】 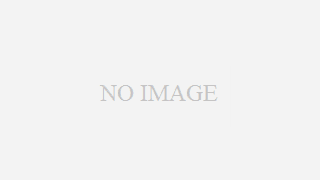 【神社めぐり】
【神社めぐり】 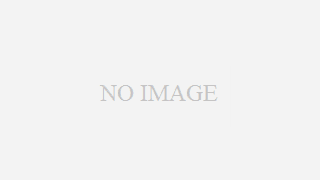 【神社めぐり】
【神社めぐり】 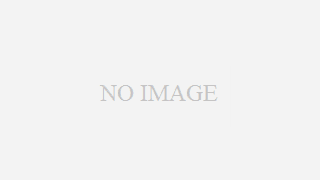 【神社めぐり】
【神社めぐり】 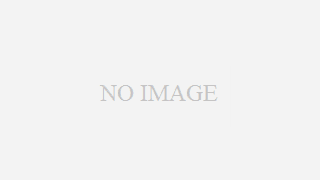 【神社めぐり】
【神社めぐり】