**建内宿禰(たけのうちのすくね)**は、
古代日本の伝説的な臣下(公卿・官吏)として知られ、
天皇に仕えた名臣・忠臣の象徴的な存在です。
日本書紀や古事記にも登場し、
政治や外交、国家運営において重要な役割を果たしたと伝えられています。
◆ 基本情報|建内宿禰とは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 建内宿禰(たけのうちのすくね) |
| 身分 | 古代の臣下、公卿、国家の重臣 |
| 活躍時代 | 推古天皇の頃(飛鳥時代)とも伝わる |
| 特徴 | 忠誠心・知恵・政治手腕に優れる |
◆ 歴史と伝説
建内宿禰は、
推古天皇や聖徳太子の時代に仕えたとされ、
外交交渉や政務の実務を担ったと伝えられています。
また、多くの古代氏族の祖とされることもあり、
彼を祖先と仰ぐ家系が各地に存在します。
『日本書紀』では、天皇に忠実で知恵深い人物として描かれ、
政治の安定に大きく貢献したとされています。
◆ ご神徳|忠誠・知恵・国家安定
| ご神徳 | 内容 |
|---|---|
| 忠誠心 | 天皇への忠義、国の安定を守る精神 |
| 知恵・政策 | 政治や外交の知恵、実務能力の象徴 |
| 家系繁栄 | 多くの氏族の祖として家族の繁栄を祈願 |
| 安定・和合 | 国家の安定と社会の調和を願う守護神的存在 |
◆ 建内宿禰にまつわる神社や伝承
| 場所 | 特徴 |
|---|---|
| 各地の建内宿禰を祖とする氏族の神社 | 忠誠と知恵の象徴として祀られることがある |
| 古代の氏族伝承 | 地域の歴史や伝説に深く関わる人物として語られる |
◆ 現代における意義
- 忠誠心や責任感の象徴として尊敬される
- 政治・行政やリーダーシップの模範となる存在
- 氏族の繁栄や家系の守護神としての信仰も一部に見られる
- 歴史や文化を学ぶ上での重要な人物
◆ まとめ|古代の知恵と忠誠を伝える名臣
建内宿禰は、
日本の古代政治と文化に深く関わり、
忠誠と知恵をもって国を支えた伝説的な人物です。
- 天皇に仕えた名臣の象徴
- 政治的知恵と忠誠心の体現者
- 氏族の繁栄や国家安定を願う存在

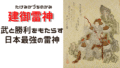

コメント